若者の危険行動を科学する
Credit: Mike Harrington/DigitalVision/Getty
15歳になるCole Skinnerは、使われなくなった採石場の上部の壁にぶら下がっていた。1台の車がやってきて停まる音が聞こえると、Coleは、友人らと大急ぎで壁から降りて、採石場の縁の上を競うように走り、有刺鉄線が張られたフェンスを跳び越えて、採石場の敷地から出た。
こうした追いかけっこは、Coleや、同じく15歳の友人Alex McCallum-Toppin、そして英国ファリンドンにある学校の生徒らにとって、楽しい遊びの1つになっている。ColeとAlexによれば、建設現場や廃墟ビルといった場所をわざわざ探して行くのは、面倒を起こすためではなく、探検するためなのだという。しかも、自慢のタネにもなる。「『廃墟になった採石場に行ってきたんだ』と言って話題を振れるからね。友達とその話で盛り上がれるんだよ」とAlexは話す。
科学ではこれまで、青年期の子どもが一枚岩的な集団になると危険行動をとるという問題は、親や社会が管理したり辛抱したりすべきものとして捉えがちだった。ノースカロライナ大学チャペルヒル校(米国)の神経科学者Eva Telzerが、家族や友人、学部生や関連分野の研究者らに、10代の青年に対する認識について尋ねたところ、「肯定的な意見はほとんどなかった」という。「これが一般的な認識なのです」とTelzer。しかし、どうしてAlexとColeが危険を冒して走ったり跳んだりするのか、こうした行動の是非と共にその社交上の価値をどう考えているのかは、神経科学から明らかになりつつある、もっと複雑な実態と整合している。青年期の危険行動は、強い反抗心や制御不能なホルモンに起因するだけではないのだと、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(米国)の神経科学者Adriana Galvánは言う。「危険行動の定義の仕方は現在、転換期にあるのです」。
若者は大人よりも危険を冒すものであり、その結果、けがを負ったり死亡したり、法に触れたり、果ては長期の健康問題を抱え込むことさえある。しかし、ここ10年の間に報告された室内実験の研究から、若者は何通りかの繊細なやり方でリスクを評価していることが明らかになってきた。10代の若者は、状況によっては年長の仲間以上に危険を回避しようとする場合もある。また、彼らが向き合うリスクは、室内実験で通常想定されるリスクよりもずっと幅広く、例えば、他者との関係から生じる社会的リスクや、スポーツチームの入団テストを受けるといった便益に関するリスク(ポジティブ・リスク)も含んでいる。こうした種類の行動は若者の脳にさまざまな影響を及ぼしていると思われる。
重要なのは、青年期におけるリスクとの付き合い方である。危険行動の根源にある神経機構を研究することで、例えば、車を運転する10代の若者に対する指針や法律をどうすべきか、あるいは、凶悪犯罪を犯した若者がどのような刑罰を受けるべきかを判断するための情報が得られるだろう。10代の若者の脳がどのようにリスクを評価しているかを解明することで、青年期に発症することの多い統合失調症やうつ病などの精神神経疾患の予測因子も見つけられるかもしれない。
10代の若者の脳内では、いろいろな意味で多くのことが進行中である。「実際、見事と言う他ありません」と、エール大学(米国コネティカット州ニューヘイブン)の神経科学者B. J. Caseyは話す。「驚くことに、たいていの場合、実に正確に進行していくのです」。
理由あっての反抗
青年期は危険の多い時期だ。全世界の15〜19歳の死亡率は10〜14歳の死亡率より約35%高い。そして、危険行動は青年期の命を脅かす要因の多くと関連している(「命に関わる危険を冒す」を参照)。世界規模で見ると、青年期の最大の死因は道路での負傷である。自傷やその他の暴力行為も上位に入っている。加えて、成人後の不健康な状態につながりかねない一部の習慣(喫煙や飲酒、座った姿勢の多い生活スタイルなど)は、10代の頃の軽率な選択に起因するものも多い。そのため、青年期の危険行動は科学者の関心事の1つとなってきた。
命に関わる危険を冒す
2015年の10~19歳の死亡者は120万人と推定されている。特に10代の後半や男性では、上位の死因の多くが危険行動と関係している。 Credit: SOURCE: WHO
「危険行動は、10代の脳に関する初期研究の多くでテーマとして取り上げられました」と、カリフォルニア大学バークレー校(米国)で青年期の脳の発達を研究するRonald Dahlは話す。「それが、助成金を獲得する手立ての1つだったのです。そのため、危険行動がクローズアップされました」。
研究初期の理論では、発達途上の脳で見られるアンバランスに注目した。特に社会学の分野で扱う、衝動性や報酬に対する強い感受性と関連する脳領域は、青年期の初期に活動が増大するが、作業記憶などの認知情報処理を司る領域は青年期を通じてなだらかに発達する。
神経科学者らは、次第に明らかになってきた10代の脳の様子を、ブレーキが利かない車でアクセルを踏み込んでいるようなものだと形容した。こうした見方は脳の発達データとは整合するものの、10代の若者の多くが危険行動をとる傾向を示さないという事実とは一致しないと、ペンシルベニア大学(米国フィラデルフィア)の精神科医Ted Satterthwaiteは話す。米国の10代の若者4万5000人以上を対象とした2016年の調査1では、17〜18歳までに喫煙を試みなかった人が61%、飲酒を一度もしていない人が約29%もいたのだ。
現在、大半の神経科学者は、各種の神経系の発達速度がそれぞれ異なるからといって必ずしも脳がアンバランスな状態だとはいえないことを認めている。「不安定でもろい時期ですが、彼らの脳がどうかしているからもろいわけではないのです」とSatterthwaite。
そうしたことから、より広範なリスクや環境による影響に注目する方向に研究がシフトしてきた。Dahlによれば、多くの10代にとっては、比較的安全な経験の中にリスクがあるのだという。例えば、友人をかばったり、誰かをデートに誘ったりするといった経験だ。「人間関係に影響を与え得る社会的リスクを負うこと。若者はこれをより鋭く感じ取るのです」。
青年期の社交術
近年の研究で、社会的要素が危険行動に影響を与える仕組みが明らかになり始めている。2009年、テンプル大学(米国フィラデルフィア)の心理学者Laurence Steinbergは、機能的磁気共鳴画像化(fMRI)装置に10代の被験者を寝かせ、「チキンゲーム」のビデオゲームをプレーさせた。被験者はゲーム内で車を運転し、6分で20カ所の仮想の信号機を通過する。最初の信号が黄色に変わったとき、車を走らせ続けることを選ぶ被験者もいれば、信号が青になるまで待つ被験者もいた。全速力でうまく通り抜ける場合もあれば、衝突事故を起こす場合もあった。
10代の被験者が1人でゲームをプレーした場合、危険を冒す頻度は成人とほぼ同じだった2。ところが、Steinbergが被験者に「君の友人が隣の部屋から見ているよ」と告げた場合、被験者が危険を冒す頻度は増した。Telzerが同僚らと行った同様の研究3では、自分の母親が見ていると告げられた10代の被験者は危険をあまり冒さなかった。fMRI装置のスキャン像から、友人の存在に影響を受けた危険行動に伴って、脳内の腹側線条体をはじめとする報酬感受性領域がより活性化していることが明らかになった。一方、母親がいると、認知制御に関与することが分かっている前頭前皮質という領域が活性化した。
神経科学者らはこのゲームを使って、10代の若者が危険を冒す傾向が、彼らの社会的地位によってどのように左右され得るかを調べてきた。オレゴン大学(米国ユージーン)の研究チームは被験者の青年に、他の10代の若者2人が見ていることをまず伝えた上で、fMRI装置内でこのゲームをプレーしてもらった4。その後、被験者に別のビデオゲームをプレーしてもらう。こちらのゲームでは、「チキンゲーム」を端から見ていた2人の若者と被験者がキャッチボールを行うが、被験者はこのゲームで仲間外れにされた。
こうした社会的疎外を経験した後に「チキンゲーム」に戻ったとき、前回より仲間のことが気になるようになったと話した被験者は、より危険を冒すようになった。このパターンを示した被験者では、他者の思考のモデリングに関与する「側頭頭頂接合部」という脳領域が強く活性化されていた。また別の研究5でTelzerらは、社会的にひどく疎外されたりイジメにあったりした10代の若者ほど、より危険を冒すことを見いだした。この研究は、最も脆弱で攻撃されやすい人々を理解する活動の一環として行われたものだ。「どういう経緯で、10代の若者が喫煙したり、良い判断や悪い判断を下したりするかが分かれば、もっとポジティブな状況へ若者を誘導できるでしょう」とTelzerは言う。
同年代の仲間がポジティブな影響をもたらす場合もある。2014年の研究6では、10代の被験者に、10人の仲間が見ているという設定で、オンラインゲームの中でお金を寄付するか手元に置くか、どちらかを選ぶよう指示した。被験者が寄付を1回して仲間がそれに賛同した場合(親指を立てた形のアイコンで賛同を示す)、その被験者はゲーム全体を通じてより多くの寄付をした(逆に賛同がないと、寄付は少なくなった)。「10代の若者は、友人たちと一枚岩的に結束すると負の影響を及ぼすようになる、という仮説もあります」とTelzerは言う。実像はもっと複雑なのである。
興味深いことに、「健全でない危険な行動」に関与するのと同じ脳内システムは、10代の若者がポジティブ・リスクを取るのを助けてもいるようだ。10代の若者のポジティブな行動と危険の多い行動のどちらでも、腹側線条体の活動、特にドーパミン受容体数の増加が観察されているからだ。この脳領域の活動は、報酬に対する感受性の高さと関連付けられている。
Telzerの研究7では、お金の寄付などで他者を助けようと決心する際に腹側線条体の活動が高まった10代の被験者は、長期的に見てあまり危険を冒さず、成人後にうつ病になるリスクも低かった。「この結果はまさに、陰と陽のような関係にあることを示しています」とDahl。
実験に基づくこうした研究には限界がある。fMRI装置内で10代の社交生活を再現することはできないからだとGalvánは話す。「火曜日の午後に寒々しい実験室の中で、土曜日の夜に起こる出来事をどうやって再現できるというのです」。彼女によれば、そうした実験室の研究は、10代の若者が現実世界で危険な行動をとる可能性よりも、危険行動を起こす性向を捉える方が向いているという。
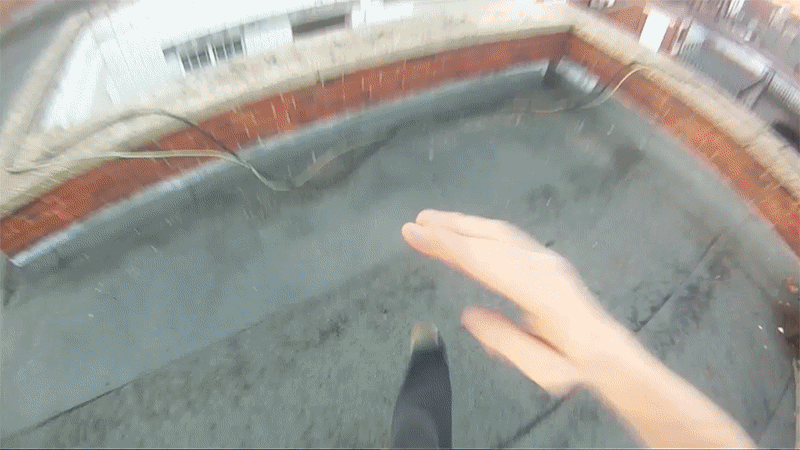
GoodSport.Video/Getty
もう1つの問題は、研究で被験者になる平均的な10代の若者では、危険を冒す傾向はさほど高くないということだ、「我々が青年期の危険行動について知っていることの多くは、実際には、高レベルの危険行動をとる若者ではなく、かなり規範的な標本集団から得られたものなのです」とTelzer。重大な危険行動は10代の若者の一部に限定されるのかもしれない。彼らのリスク対処法が同年代の仲間と大きく異なっていることを示す証拠もある。
ハイリスク集団の研究
Telzerは2015年に、重大な犯罪が理由で退学になった青年らを被験者として研究を行った(成果は未発表)。被験者にはfMRI装置内で寝てもらい、スクリーンに文字が見えたときにはボタンを押すが、スクリーンに「X」が表示された場合にはボタンを押さないという課題をやってもらった。スクリーン上には、10代の若者が笑っていたり浜辺でゲームをしたりしている「ポジティブ」な写真や、誰かを集団で攻撃している「ネガティブ」な写真といった、社会的な意味を含む写真も映し出された。被験者の大半は、表示された画像がポジティブだったときに課題の成績が悪くなった。これはつまり、彼らの認知制御が、報酬を思い起こさせる写真によって無効にされたからだ。腹側線条体の活動はそれと歩調を合わせて上昇した。ところが、退学や停学の処分を受けた生徒では、ネガティブな写真を表示した場合に課題の成績が悪くなった。Telzerはこの結果から、退学や停学の処分を受けた10代の若者に見られる自制心の欠如は、社会的な刺激に対する別種の反応が原因なのではないかと考えている。
これまで、重大な危険行動をとる若者は、標準的な10代のうち極端な特徴を持つ脳の持ち主だと考えられてきたとTelzerは話す。しかし、彼らはおそらく「全く違うタイプの若者」なのだと彼女は言う。
Credit: Monty Rakusen/Cultura/Getty
危険行動に関する研究から、米国の司法制度に役立つ情報が得られ始めており、例えば、10代の若者の自制心を損なう恐れのある複数の要因を、関係省庁が考慮するようになってきている。感情的でない状態の18〜21歳の若年成人は、それより年上の成人と同じくらい十分に認知機能課題をこなせることが分かっている8が、感情的な状態になると若年成人の成績は低下する。この研究や他の研究から、感情的に「冷めた」状態での犯罪は、感情に引きずられ「カッとなって」起こした犯罪とは別物として考えるべきだと思われる。同様の研究から、危険なことをするリスクの高い10代の若者を正確に見つけ出す方法も分かるかもしれない。
Steinbergは2017年、5件の裁判事件で、青年に科す刑に関して証言した。彼は、10代の若者の判断力が感情によっていかに影響を受けるかを証言し、それを聴聞したケンタッキー州の裁判所は同年、死刑の適用年齢を21歳に引き上げることを決定した。この証言はさらに、21歳未満の犯罪者に対して仮釈放なしの絶対的終身刑を科すことへの反対意見にも盛り込まれた。
科学者らは、こうした若者の発育に関する研究が、政策のための情報として役立つのではないかと大いに期待を寄せている。しかし中にはSatterthwaiteやGalvánのように、個々の事例を扱う裁判でfMRIデータを使うことには、いくつか課題があると指摘する研究者もいる。神経活動を画像化して得られるデータは通常、被験者全体を平均化したものであり、そのため、どれか1人の脳についてfMRIデータから結論を引き出すのは危険である。「率直に言って、私は神経画像化技術を使うべきでないと思います。あまりにノイズが多いからです」とSatterthwaite。
fMRIのデータは診断用としてもノイズが多すぎる。しかし、若者の脳がリスクに対して示す反応から、うつ病や不安神経症の初期症状を明らかにできる可能性を示した証拠が得られており、Satterthwaiteは現在、fMRIを用いた診断に関心を持っている。彼は、臨床で治療方針を立てられるようなところまで研究が進んでほしいと考えている。「命に関わる状態でやって来た人を、診断検査も画像診断も臨床検査もせずに追い返すなんて、まるで中世ですよ」と彼は言う。
青年期のリスクに関する広範な研究は、すでに、日常生活における危険行動を最小化するのに役立っている。例えば、睡眠時間が不十分な青少年は、喫煙や性行為などの危険行動をとる傾向が強い。学校の始業時間を遅らせて睡眠時間を増やす取り組み(米国疾病管理予防センター〔CDC〕や米国小児科学会〔AAP〕などの組織が後押ししている)の影響を調べた数十件の研究からは、青少年の抱える危険行動などの問題の多くは、始業時間の繰り下げで改善されることが示唆された9。AAPは始業時間を8:30かそれ以降に設定することを推奨し、それを受けて米国では数百校が始業時間を遅らせたが、2014年の段階で中学校の始業時間の平均はまだ8:00だった。
Steinbergは、若者が最初にリスクにさらされる機会を制限すべきだと主張している。例えば、タバコを購入できる年齢を21歳以上にしたり、学校の周囲300m以内での酒類販売を禁止したりするなどだ。こうした取り組みの方が、生徒らにリスクを教え込むよりもずっと効果があるだろうと彼は言う。他に、危険行動をとる機会を封じるための政策もある。オーストラリアやニュージーランド、北アイルランド、米国の「段階的な運転免許取得の制度」では、若年ドライバーは経験を積むまで、10代の同乗者しかいない状態で運転してはいけないことになっている。こうしたプログラムにより、事故による若年ドライバーの死傷数が減少することは、すでに明らかになっている。
しかしCaseyによれば、ちょっとしたリスクを経験することは無駄ではないという。「危険を冒すのをやめてほしいなどと言うつもりはありません。経験を積むことで、大人になって安全な状況で暮らすことができるのです」と彼女は話す。
若者には、独立していく過程で学ぶべきことが多くあり、それがたやすいことだと言う者はいない。「子どもの成長期でこれより難しい時期があるとは思えません」とCaseyは話す。「講演をするときはいつも、青年期をまたやり直したいと思う人に挙手してもらうのですが、誰も手を挙げませんね」。
翻訳:船田晶子
Nature ダイジェスト Vol. 15 No. 5
DOI: 10.1038/ndigest.2018.180517
原文
Sex and drugs and self-control: how the teen brain navigates risk- Nature (2018-02-22) | DOI: 10.1038/d41586-018-02170-3
- Kerri Smith
- Kerri Smithは、Natureロンドン編集部のNews Feature担当。
参考文献
- Johnston, L. D. et al. Monitoring the Future: National Survey Results on Drug Use, 1975–2016 — 2016 Overview, Key Findings on Adolescent Drug Use (Univ. Michigan, 2017); available at http://go.nature.com/2ngttbt
- Chein, J., Albert, D., O’Brien, L., Uckert, K. & Steinberg, L. Dev. Sci. 14, F1–F10 (2011).
- Telzer, E. H., Ichien, N. T. & Qu, Y. Soc. Cogn. Affect. Neurosci. 10, 1383–1391 (2015).
- Peake, S. J., Dishion, T. J., Stormshak, E. A., Moore, W. E. & Pfeifer, J. H. Neuroimage 82, 23–34 (2013).
- Telzer, E. H., Miernicki, M. E. & Rudolph, K. Dev. Psychopathol. 30, 13–26 (2018).
- Van Hoorn, J. et al. Res. Adolescence 26, 90–100 (2016).
- Telzer, E. H., Fuligni, A. J., Lieverman, M. D. & Galván, A. Proc. Natl Acad. Sci. USA 111, 6600–6605 (2014).
- Cohen, A. O. et al. Psychol. Sci. 27, 549–562 (2016).
- Wheaton, A. G., Chapman, D. P. & Croft, J. B. J. Sch. Health 86, 363–381 (2016).
